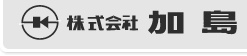|
電熱という言葉が私たちの意識の中に、そして、生活の中に入ってきたのは戦後のことといわれています。
戦後、破壊された都市の中で一躍脚光を浴びたのが電気コンロ。当時は、素焼きの熱板に鉄クロームの電熱線を入れたばかりのアルミ台に取り付けられたものでした。
その後、昭和25年を境に電気洗濯機、電気掃除機、電気冷蔵庫が登場。三種の神器として主婦のあこがれの製品となりました。また、電気毛布、トースター、ヘアドライヤー、電気ポット、石英管ヒーターなど電熱器を利用した様々な商品が巷を賑わすようになっていきました。
特に、昭和35年に東芝が開発した自動式電気釜はヒット商品となり、昭和40年にはすでに電子レンジが登場していました。布団乾燥機、電気ジャーポット、縦型電気ストーブなど日本独特の製品群もあります。 |

|
希土類といわれ、土の中にわずかにしか含まれない金属の代表は金ですが、同じ種類にニッケルがあります。
ニッケルはステンレス合金にも使用され、高価な金属で18-8ステンレスとは18%クロム8%ニッケルという含有量をさしています。ステンレス合金の価格はニッケルの含有量で決まるといわれるそのためです。
そのニッケルとクロムを含有し素材が鉄でできているのがニクロム線です。ニクロム線はその名の通りニッケルとクロムを含有した線材であることをさしています。
ニッケルとクロムを含有させるのは熱や酸化に対して強くなるというのが理由で、切れにくく長期間使用できる発熱体に適した材料の代表的なものです。 |

|
上記の線材に通電し発熱される方法と、電磁誘導という方法を用いた方法が代表的なものです。
電子レンジ、IH式調理機器は高周波を利用して加熱しています。 |

|
発熱体の温度が上がりその熱を空気や暖めたいものに直接伝える伝導加熱と、赤外線が放射される輻射加熱があります。素材や発熱方法を変えることで遠赤外線を多く放射するものや近赤外線を多く放射するものなど造り分けられています。用途に合わせ化粧品や食品から自動車の焼き付け塗装まで幅広く使用されています。 |

|
燃焼を利用した加熱方法と大きく違うところは酸素を消費せずに加熱できるというところです。
水の中や閉めきった部屋の中でも安定した発熱が可能です。
化粧品や食品などの臭いに敏感な製造ラインで燃焼バーナー(石油バーナーなど)が使えないところでは進んで使用されています。また、長時間の煮込み作業が必要となる飲食店においても、人が帰った夜間でもつけっぱなしにできるという理由から数多く導入されています。 |